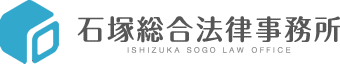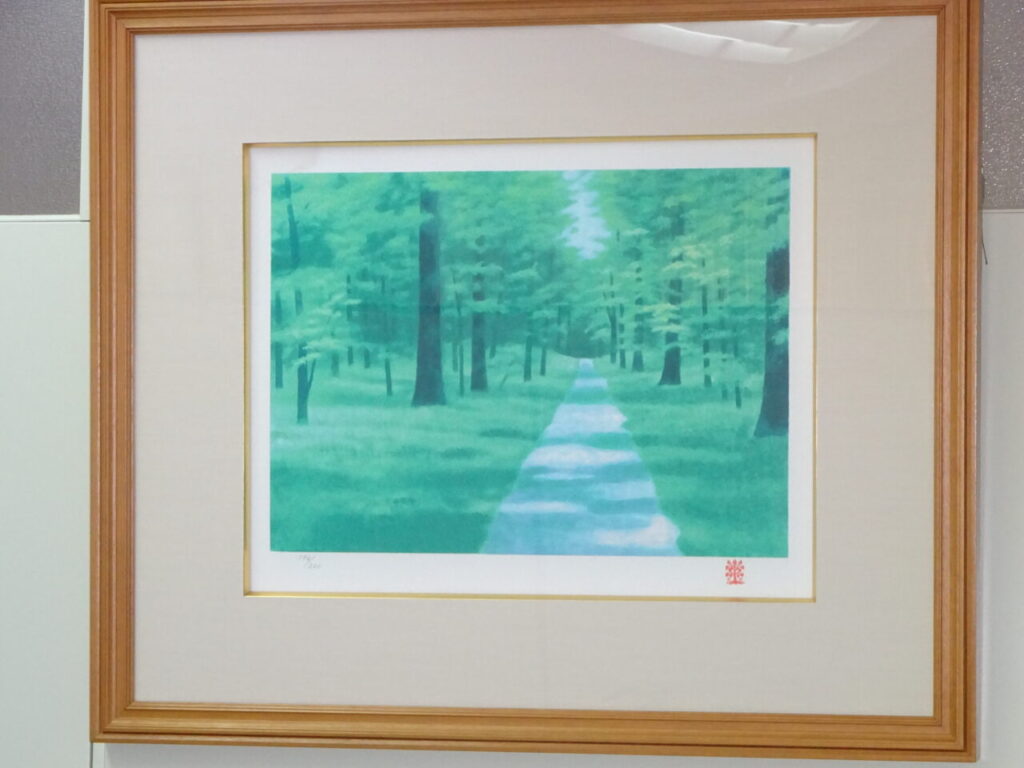今回は「改正相続法21 持ち戻し免除の意思表示の推定3(民法第903条第4項)です。
前二回に引き続いての持ち戻し免除の意思表示の推定に関するお話です。
私としては、持ち戻し免除の意思表示の推定が直接問題となるわけではないのですが、実務上、Q1の設問において、この持戻し免除の意思表示の推定規定が間接的に重要な効果を及ぼすことになるのではないか、弁護士としてしっかりとこの持ち戻し免除の意思表示の推定規定を押さえておく必要があるのではないかと思っております。
少し難しいけど、ためになるのが今回です。
Q1 私と夫の婚姻期間は20年以上ですが、夫は遺言書で自宅を私に「相続させる」と記載しており、「贈与する」と記載しておりませんでした。遺言書に記載されていない遺産があり、その遺産分割が問題となる場合、「相続させる」と記載された自宅に、持ち戻し免除の意思表示は推定されるのでしょうか。
A1 「相続させる」と記載された場合には持ち戻し免除の意思表示は推定されません。もっとも、居住用不動産以外の遺産分割において、自己の法定相続分を主張できる可能性はあるでしょう。
「相続させる」と記載された遺言書を、特定財産承継遺言といいいます。判例上、特定財産承継遺言は、遺贈又は贈与とは異なり、「遺産分割方法の指定」とされております。実務では、この「相続させる」と記載された遺言書は大変多いです。「遺贈」よりも多いでしょう。これは、不動産について、遺贈の場合には登記申請を共同申請する必要があるのに対して、遺産分割方法の指定の場合には単独申請が可能という違い、効果が大きいと思います。
いずれにしましても、遺産分割方法の指定とされ、遺贈と区別されている以上、居住用財産を「相続させる」と記載された遺言書には、「遺贈又は贈与」がなされた場合と規定されている民法第903条第4項を直接適用することはできないことになります。
したがって、遺言書において被相続人がその配偶者に自宅を「相続させる」と記載されている場合、民法第903条第4項の直接適用によって持ち戻し免除の意思表示を推定することはできません。
では、このときに遺言書に記載されていない他の財産(預貯金等)がある場合、配偶者は居住用不動産という特別受益を受けていることを理由に、自己の法定相続分を主張することはできないのでしょうか。
この問題は、持ち戻し免除の意思表示の推定の問題というよりも、遺言書に記載されていない遺産の分割方法をどうするのかという、遺言者の意思解釈の問題になります。
本件のような場合、遺言者の意思解釈には、次の2つの考え方が成り立つと思います。①遺産分割方法の指定を受けた相続人の具体的相続分は既に指定を受けた遺産の額を控除するという考え方と、②遺産分割方法の指定がなされた財産は別のものとして考慮の範囲外として、残りの遺産を法定相続分で分けるという考え方です。
前者のように考えるのであれば、特別受益の持ち戻しがなされたままということになりますし、後者のように考えるのであれば、持ち戻し免除の意思表示が推定されたのと同じ結論になります。
さて、設問にあるように、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなされた、居住用不動産を「相続させる」という遺言書がある場合の遺言者の意思について、上記①②いずれのように考えるべきでしょうか。
具体的事情をもとに検討することになるでしょうが、遺産分割方法の指定をした遺言者は、居住用不動産以外の遺産に対する配偶者の取り分を減らす意図はなかったと考えられることが多いのではないでしょうか。
そのため、「相続させる」との遺言書によって居住用不動産を取得することになった場合にも、他の遺産の取得を諦めるべきではないと思います。この辺りになると、法律的な知識が無いと難しいところがありますので、是非弁護士に相談されるべきと思います。
Q2 私と妻の婚姻期間は20年以上ですが、私は以前妻に自宅を生前贈与したことがあります。しかし、妻はその後私の面倒を見ず遊び歩いているので、自宅の贈与を特別受益として持ち戻させたいのですが、可能ですか。
A2 持ち戻し免除の意思表示はあくまでも推定されるというだけですから、ご本人がそれと異なる意思を表示すること、つまり特別受益として持ち戻させることは可能です。
あくまでも民法第903条第4項は被相続人の意思を「推定する」規定ですから、被相続人がこれと異なる意思を表明することは可能です。
そして、この異なる意思の表明ですが、「遺言書」の中で表明してもいいですし、それ以外の方法で表明することも可能です。
持ち戻し免除の意思表示の推定に関するその他の記事