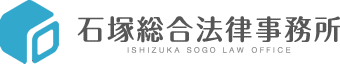おかげさまで5周年
今後も,柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に支えていただきながら,良質な法的サービスを提供することで,地元柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に貢献していきたいと思います。6年目も,石塚総合法律事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。
2022.02.1
改正相続法13 相続による権利の承継と対抗要件主義2(民法第899の2条)
相続により法定相続分を超える債権を取得した受益相続人が対抗要件を具備する方法には、①共同相続人全員(又は遺言執行者)による通知、②受益相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにしてする通知、③債務者の承諾があることになります。
2022.01.29
改正相続法12 相続による権利の承継と対抗要件主義(民法第899の2条)
改正相続法では、相続を原因とする権利変動についても、これによって利益を受ける相続人は、登記等の対抗要件を備えなければ法定相続分を超える権利の取得を第三者に取得することができないことにしました。
2021.11.16
改正相続法11 特別の寄与3(民法第1050条)
特別の寄与を相続人との話し合いで定めることができるのであれば話し合いで定めることができます。話し合いができない場合には家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。
2021.11.1
改正相続法10 特別の寄与2(民法第1050条)
特別の寄与といえるためには、療養看護が無償であることが必要です。この無償であるか否かについては、当事者の認識や、当該財産給付と労務提供の時期的、量的な対応関係等を考慮して判断されると考えられております。
2021.10.24
改正相続法9 特別の寄与1(民法第1050条)
特別の寄与制度によって,相続人以外の親族が被相続人に療養看護した場合も,その親族は相続人に療養看護した分(特別の寄与分)のお金を払ってくれと請求することができるようになりました。
同制度は,相続人以外の親族の貢献を正当に評価することができるようになったというプラス面はありますが,ともすれば相続問題の終局的解決が長引くというマイナス面もあるように思われ,実務家としては少し複雑な気分になります。
2020.11.14
改正相続法8 遺産の一部分割(民法第907条)
今回は,改正相続法8 遺産の一部分割(民法第907条)です。 Q1 父の遺産は自宅(土地・建物)と預貯金です。共同相続人の弟と自宅の帰属…
2020.10.7
改正相続法7 遺産分割前における預貯金の払戻し制度2(民法第909条の2)
民法第909条の2後段によって,同条前段により権利行使がされた預貯金債権については,その権利行使をした共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなすことにしています。
2020.09.25
改正相続法6 遺産分割前における預貯金の払戻し制度1(民法第909条の2)
民法第909条の2によって権利行使することができる預金債権の割合及び額の計算式は,以下のとおりです。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分=単独で払い戻しをすることができる額
※ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。
2020.08.22