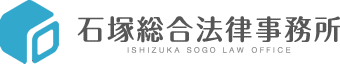改正相続法シリーズの4回目,遺留分侵害額請求4(民法第1046条第2項第2号)です。これで遺留分侵害請求権の回は終了となります。
遺留分侵害額請求はとても専門的でただでさえ理解しにくいのに,このブログでは専門的な情報,知識を書いているので,こんなの書かれてもわからないと思われることが多いかもしれません。
こんなの書いてもわかってもらえないと思いつつ,今回も遺留分侵害額請求の最後を飾るにふさわしい,難易度かなり高めの内容となっております。
まず,今回は遺留分侵害額の計算方法が前提知識として必要なので,計算式を載せておきます(詳しくは遺留分侵害額請求2参照)。
Ⅰ 遺留分侵害額=遺留分額(A)
-遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額(B)
-遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額(C)
+遺留分権利者が負担する債務の額(D)
Ⅱ 遺留分額(A)=遺留分を算定するための財産の価額(a)×個別的遺留分
Ⅲ 遺留分を算定するための財産の価額(a)=相続開始時に被相続人が有した積極財産の価額(①)
+贈与財産(②)
-相続債務の全額(③)
以下本題
Q まだ遺産分割をしていない遺産分割対象財産があります。遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額(上記C)は法定相続分を前提に計算すればいいですか,具体的相続分を前提に計算すればいいですか?
A 遺産分割が既に終了しているか否かを問わず,具体的相続分を前提にして遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額(上記C)を計算することになります(ただし寄与分については考慮しない)。
改正前は,遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額(上記C)を計算するにあたり,法定相続分を前提とするのか,具体的相続分を前提とするのかについて判断が分かれていましたが,新しい相続法によって具体的相続分を前提とすることに定められました。
これは,遺留分侵害額請求が問題となる事案は,通常生前贈与等の特別受益がある場合が多いにもかかわらず,遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額を算定する際に特別受益の存在を考慮しない考え方(法定相続分説)を採用すると,その後に行われる遺産分割の結果との齟齬が大きくなり,事案によっては,遺贈を受けている相続人が,遺贈を受けていない相続人に比して最終的な取得額が少ないという逆転現象が生ずる場合があり,相当ではないと考えられるからです。
この説明だけではわかりにくいので,(事例で考えてもわかりにくいですが)事例で考えてみましょう。
相続人は,被相続人の妻A(法定相続分は2分の1),長男B(法定相続分は4分の1),次男C(法定相続分は4分の1)の3人です。
被相続人には1000万の預金がありました。また,長男Bに1000万の現金,第三者Dに8000万相当の土地を遺贈しました。相続時に借金はありませんでした。
法定相続分説を採用した場合
[遺産分割]
Aの具体的相続分=(1000万+1000万)×1/2=1000万
Bの具体的相続分=(1000万+1000万)×1/4-1000万=-500万
Cの具体的相続分=(1000万+1000万)×1/4=500万
Aの取得額=1000万×1000万÷(1000万+500万)≒666万6667
Bの取得額=0
Cの取得額=1000万×1000万÷(1000万+500万)≒333万3333
[遺留分]
Aの遺留分侵害額=(1000万+1000万+8000万)×1/2×1/2-1000万×1/2=2000万
Bの遺留分侵害額=(1000万+1000万+8000万)×1/2×1/4-1000万-1000万×1/4=0
Cの遺留分侵害額=(1000万+1000万+8000万)×1/2×1/4-1000万×1/4=1000万
[結果]
Aの最終的な取得額=666万6667+2000万=2666万6667
Bの最終的な取得額=1000万
Cの最終的な取得額=333万3333+1000万=1333万3333
Dの最終的な取得額=8000万-2000万-1000万=5000万
(注:Bの遺贈についてはBの遺留分の範囲内なので負担なしとなり,遺留分侵害請求を受けるのはDのみとなるので,上記結果となります。受遺者等が相続人の場合の遺留分侵害請求の負担の上限につき,改正相続法3 遺留分侵害請求3を参照。)
法定相続分説によると,上記の結果のように,遺贈を受けたBが遺贈を受けていないCよりも最終的な取得額が少なくなるという逆転現象が起きてしまうのです。
具体的相続分説を採用した場合
[遺産分割]
上記と一緒。
[遺留分]
Aの遺留分侵害額=(1000万+1000万+8000万)×1/2×1/2-666万6667=1833万3333
Bの遺留分侵害額=(1000万+1000万+8000万)×1/2×1/4-1000万-0=250万
Cの遺留分侵害額=(1000万+1000万+8000万)×1/2×1/4-333万3333=916万6667
[結果]
Aの最終的な取得額=666万6667+1833万3333=2500万
Bの最終的な取得額=1000万+250万=1250万
Cの最終的な取得額=333万3333+916万6667=1250万
Dの最終的な取得額=8000万-1833万3333-250万-916万6667=5000万
このように,具体的相続分説によると,上記の結果のように,遺贈を受けたBが遺贈を受けていないCよりも最終的な取得額が少なくなるという逆転現象が起きない。
なお,上記の計算方法は遺産分割が終了した場合でも変わりません。遺産分割が終了した場合については,現実に分割された内容を前提に控除すべきという考え方もありましたが,これだと,遺産分割手続きの進行状況如何によって遺留分侵害額が変動し,これにより遺留分権利者に帰属した権利の内容が変動することになって相当でないと考えられたからです。
以上で,改正相続法の遺留分侵害額請求は終了となります。
これまでの遺留分侵害額請求のブログは以下のとおりです。
(改正相続法1 遺留分侵害額請求1(民法第1046条第1項,第1047条第5項))