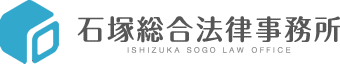離婚調停事件を代理するときに,よく質問されることの1つに,離婚調停が成立した後どうしたらいいですか?というものがあります。
当ホームページでは,こちらのページの下段にある,「弁護士が教える離婚について知っておきたい基礎知識」の9つの項目において,離婚に関する事項を,かなり詳しく説明していますが,離婚後の手続については,それほど触れていないので,これからしばらくの間,連載という形で説明していきたいと思います。
今回は,「調停離婚後の手続1 調停離婚成立後の離婚届について」を説明したいと思います。
まず,前提のお話しから。
Q1 離婚調停が成立したとして,離婚が成立するのはいつでしょうか。
A1 合意内容によりますが,通常は調停が成立した日が離婚が成立した日です。
よくある合意内容である,「申立人と相手方は,(相手方の申し出により)本日,調停離婚をする。」と調停調書に定められたなら,離婚調停が成立した日に離婚が成立することになります。その後に,離婚届を届出ることになりますが,それは報告的届出といい,離婚の成立には影響しません。
まれに,調停の場で離婚届を作成した上,「申立人または相手方の一方が責任をもって離婚届を役所に届出る」という合意をした場合には,離婚届を役所に届出して受理されたときに離婚が成立します。
前者によるとき,戸籍に「離婚の調停成立日」と記載されるため,戸籍から調停離婚であるとわかるようになります。それを嫌う場合に,後者の合意をすることもあります。しかし,後者によると,提出義務者が離婚届を届出ないかぎり,離婚が成立しません。そのようなリスクを抱えた合意は望ましくないので,後者の合意をすることは稀といえるでしょう。
したがって,合意内容にはよりますが,実際には,前者の合意が交わされるので,離婚調停が成立した日に離婚が成立するといっていいでしょう。以下も,前者の合意が交わされたことを前提にお話しを進めたいと思います。
Q2 調停離婚が成立したら,離婚届を届出なくてもいいのでしょうか。
A2 離婚届を届出なければなりません。
しかも,離婚が成立してから10日以内に離婚届を市区町村に届出なければなりません。仮に,10日以内に離婚届を届出なければ,(状況次第では)過料という,金銭的な制裁を科されることもあります。
10日もあれば充分だ,と思われるかもしれませんが,実際には,この期間はかなり短いといえます。
なぜなら,離婚届と一緒に提出する,「調停調書謄本」を手にするのに数日かかるのが一般だからです。調停証書は調停成立後に,裁判所の書記官が作成するので,調停成立時に調停証書謄本を受け取れるわけではありません。そして,調停調書謄本を郵送してもらうときには,郵送にかかる日数分,受取りが遅くなります。
また,離婚届を本籍地のある市区町村に届出れば問題ありませんが,本籍地が遠方にある等の理由から,本籍地以外の近隣の市区町村に届出をする場合,戸籍謄本を提出しなければなりません。この戸籍謄本を離婚後に郵送で取り寄せようとすると,取り寄せるまでの間,離婚届を届出ることができないことになります。
したがって,10日以内という期間は,思っている以上に短いのです。
もっとも,こうした事情は,市区町村の職員もわかっているので,多少遅れても,事情を説明すれば,問題なく受け取ってくれることが多いとは思います。上記に,(状況次第では)と書いたのは,そのためです。
Q3 離婚届には,他方の署名や証人の署名が必要なのでしょうか。
A3 調停離婚後に提出する離婚届には,届出をする者の署名のみで足り,他方の署名や証人の署名は不要です。
他方の署名や証人の署名がなくとも,調停調書謄本により,離婚が成立したことが明らかなので,これらの署名は不要なのです。
Q4 離婚届は,離婚調停の申立人,相手方,いずれが提出するのですか?
A4 離婚届をいずれが提出するかは,調停調書の記載によります。
具体的には,「申立人と相手方は,本日,調停離婚をする。」と記載された場合には,申立人が届出をし,「申立人と相手方は,本日,相手方の申し出により,調停離婚をする。」と記載された場合には,相手方が届出をすることになります。
ですから,調停調書の内容を取り決めるときには,自分が離婚届を届出る義務を負うのかを意識して取り決める必要があります。
一般には,婚姻時に姓を変えて相手方の戸籍に入った方が離婚届を届出る義務を負うことが多いです。これは,婚姻時に姓を変えて相手方の戸籍に入った者は,離婚後の戸籍として,旧戸籍(例えば,両親の戸籍)か,新戸籍(新たに作成する自分の戸籍)かを選択することができるところ,離婚後の用紙に,その選択結果を記載しなければならないので,婚姻時に姓を変えて相手方の戸籍に入った者が離婚届を記載し,届出た方が,その選択結果を正確に離婚届に反映させることができるからです。相手方に任せてしまうと,自分の選択とは異なる戸籍に入ってしまうおそれがあります。
Q5 離婚届を届出る義務を負う者が,離婚届を届けなかった場合,離婚の成立は無効になるのですか。
A5 離婚届を届出なくても,離婚の成立は無効になりません。
前述のように,調停の成立日に離婚は成立しており,離婚届は離婚の成否には影響がありません。離婚届を届出る義務を負う者が離婚届を届出ない場合,他方の者が離婚届を届出ることもできるようになります。

調停離婚後の手続1 調停離婚成立後の離婚届について
もう去年のことになるのでしょうか,平成29年12月6日に,受信設備を設置した人はNHKと受信契約を締結しなければならないとする規定,放送法64条1項を合憲とする最高裁判決が出ました。
同判決により,受信設備を設置している人は,NHKから裁判をされれば,受信契約を締結しなければならなくなり,そして,同契約の締結は,判決日からではなく,受信設備を設置した日からとなるため,受信設備を設置した日からの受信料を支払わなければならないことになりました。
そのため,受信設備を設置したのが10年前,20年前なら,10年分,20年分の受信料を請求される恐れが出てきたのです。
同判決によって,NHKが,過去分を含めて,高額な受信料を積極的に請求してくるのではないかと危惧されております。確かに,受信料を払って下さい,支払わないなら,裁判をすることもありますよといわれれば,今までと違い,支払に応じる人も出てくるでしょうから,その可能性は低くないでしょう。
もっとも,本当に10年分,20年分の受信料を支払わなければならないのでしょうか?
答えはノーです。
NHKの受信料の消滅時効期間は5年ですから,5年を超えて受信料を求められた場合には,消滅時効を援用することで,支払わなければならない受信料を減額させることができます。
なお,NHKは,消滅時効期間が5年であることは当然に知っていますが,同期間を超えて,設置日からの受信料を請求してきます。
ですから,10年前,20年前といった,随分前の受信料の支払いを請求されたときには,慌てないで,消滅時効を援用できないか,弁護士に相談して下さい。
突然,ブログでNHKの受信料を話題にしたのは,弊事務所においても,まさにNHKから高額な受信料の支払いを求められ,これを時効援用で減額したという事案があったので,一言書き留めておきたいなと思ったからです。

佐倉支部の新館(地裁・簡裁)

佐倉支部の本館(家裁)
佐倉支部に行ったのは今回が初めてではなく,実は何回も行っています。佐倉支部管轄の事件も意外にあるのです。
佐倉支部は小高い丘の中腹にあるため,電車で行くと,京成線の佐倉駅から坂道をしばらく登らなくてはなりません。
佐倉支部に限らず,裁判所は小高い場所にあることが少なくないんです。(ホームグランドである)松戸支部も小高い場所にありますし,福島県だといわき支部も小高い場所にあります。
城跡や旧日本軍の施設跡地に,裁判所が建てられたことが少なくなかったことが原因ではないかと,勝手に推測しております。
佐倉支部は,佐倉城の城主土井利勝が建てた松林寺や,佐倉城の鎮守麻賀多神社や,旧佐倉藩校(佐倉高等学校)の近くにあるので,「なんか」関係しているのではないかなとか思いながら,いつもテクテク坂を登っております。
弊事務所では,今後の事務所運営をよりよいものとするために,事件終了時に,依頼者様に任意でアンケートを書いていただいております。
お客様の声が続々寄せられて来ました。
https://ishizuka-law.jp/voice/
お客様の声が,これから弊事務所へのご相談やご依頼を考えている方の参考になれば幸いです。