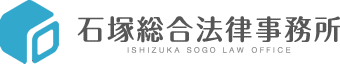今回は、改正相続法16 配偶者居住権3です。
これまでは、配偶者居住権の成立要件、配偶者居住権の内容について説明してきました。
今回は、配偶者居住権の消滅について説明します。
Q1 長年父に連れ添っていた母が、父の相続時に私が相続した実家について、配偶者居住権を主張することになりました。この配偶者居住権はいつまで存続するのですか。
A1 配偶者居住権は、特段の定めのない限り配偶者が死亡する時までとなります。もっとも、遺産分割協議時や審判時等において、存続期間を定め場合はその期間が到来するまでとなります。
配偶者居住権の消滅原因は、①存続期間の満了(第1036条、第597条第1項)、②居住建物の所有者による消滅請求(第1032条第4項)、③配偶者の死亡(第1036条、第597条第3項)、④居住建物の全部滅失当(第1036条、第616条の2)等があります。
Q2 遺産分割において配偶者居住権の存続期間を10年と定めたのですが、10年経過後もやはり自宅に住み続けたいと思っています。配偶者居住権の延長をすることはできるでしょうか。
A2 残念ながら配偶者居住権の延長は認められていません。存続期間満了後も自宅に住み続けたい場合は、自宅を相続した所有者との間に使用貸借契約や賃貸借契約を締結する必要があります。
配偶者居住権の評価額は、その存続期間によっても変わります。長ければ長いほどその評価額は高いことになります。存続期間を10年として配偶者居住権を評価したのに、延長や更新を配偶者居住権を適切に評価することができなくなってしまいます。そのため、延長や更新はみとめられておりません。
Q3 配偶者が自宅を勝手に第三者に貸していることがわかりました。配偶者居住権を消滅させるにはどうしたらいいですか。
A3 配偶者に対して相当の期間を定めた是正の催告を行って下さい。その期間内に是正がなされないときに、拝具者居住権を消滅させる旨の請求をしてください。
配偶者居住権は所有者の同意なくして自宅を第三者に貸すことは許されていません。そのため、勝手に第三者に貸していることが分かった場合には、配偶者居住権の消滅請求が問題となります。
もっとも、第三者に貸しているという事実だけですぐに消滅請求をすることはできません。法は、配偶者に対して是正の機会を与えております。配偶者が是正の機会があったのにもかかわらず是正をしなかった場合に消滅請求を認めることにしております。
この是正の機会が与えられているところが、配偶者短期居住権と異なるところになります。
配偶者居住権に関するその他の知識はコチラです。